
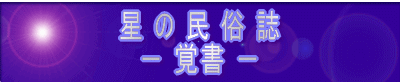
篠 田 通 弘
※ << >>中は傍点あり

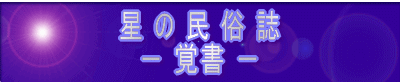
篠 田 通 弘
※ << >>中は傍点あり
1、 柳田國男編『山村生活の研究』に現れた「ムツラ星さん」 柳田國男氏指導による郷土研究所の山村50余か所の山村生活資料調査蒐集事業が始まったのは1934(昭和9)年5月のことである。1府県1か所以上、「互いに距離を有して隔離され、且つ比較的交通機関に恵まれず、所謂世間との往来の制限せられたる村落、然も従来生活調査の未だ試みられざる山村を、原則として撰んだ」(柳田國男編『山村生活の研究』1937年)として、63か村と3島の調査が3年にわたって行われた。岐阜県揖斐郡徳山村も調査対象となった1村だった。 山村生活調査項目は「郷土生活採集手帖」として1934年に作成され、1935年、1936年に増補改訂され、最終的には100項目となった。その1は「村の起り 其の言ひ伝え、一番早く開けた所、奮家」に始まり、その100は「幸福な家 仕合でよき人や家の話」へと続いている。 ところでこれら調査項目には「星の和名」「星の信仰」「星の言い伝え」などは含まれていないが、報告書である『山村生活の研究』(1937年)にはわずかではあるが「星の民俗」とも言うべき報告がある。 瀬川清子氏は同報告書で 「33 よなべ」 を担当している。これは100の調査項目のうち 「33 よなべ 夜業の季節と方法」 の報告である。その冒頭には次のように記されている。 ************************************************ よなべは秋の収穫後から始まる。雪が来るのが早いのでそれまでに稲扱きから俵に仕上げるまでの作業を片付けるには、どうしてもよなべが必要である。家中の者が小屋に集って働き、ムツラ星さんが杉の梢に来るのを合図に母屋へ引き上げる。11時頃である。 ************************************************ 瀬川清子氏の報告は大島正隆氏による山形県西置賜郡小国三村(小国本村、南小国村、北小国村)調査をもとにしている。 大島氏の調査で採集された「ムツラ星さん」とは「六連星」のことで、和名「すばる」、プレアデス星団M45(Plaiades)のことである。「すばる(六連星)」が山形県小国三村では夜なべ仕事の目安とされていたことがわかる。 山村の生活と自然との関わりで言うと、例えば農事暦と雪形の関わりなどについても調査項目からは抜け落ちている。全国各地に見られる「すばる(ムツラ星)」と農事暦との関連も調査項目としては採用されてはいなかった。にも関わらず小国三村の調査で「ムツラ星さん」が採集されているように、「すばる(六連星)」は山村の生活と切り離すことのできない「お星さん」だったことを物語っている。 郷土研究所が山村生活調査を開始した6年後、柳田民俗学は星の和名などを通して野尻抱影氏の「星の民俗」に出会うことになる。 それでは1930年代までの日本では、星と人々の暮らしとの関わりを示す「星の和名」などは一般にどのように認識されていたのだろうか。 (上図は1938年復刻原本、1975年国書刊行会より復刻版刊行、篠田所蔵本) (20220129掲載) |
| 2、 B.H.チェンバレン「日本文学には星辰の美を詠じたものがない」 バジル・ホール・チェンバレン氏( Chamberlain Basil Hall 氏自身は日本語ではチャンブレンと表記している)1850年イギリスのポーツマスで生まれた。 1873(明治6)年に来日し東京帝国大学(現東京大学)で言語学を講じた。氏は日本語学の祖と言われ、日本語を研究し、また日本文学、歴史なども研究した。 日本滞在中に彼は16冊の著書、42篇の論文、12篇の翻訳を残している(熊谷忠泰・増田史郎亮「B.H.チェンバレンの日本観」『長崎大学学芸学部 教育科学研究報告』第8集所収、1961年)。著作を内容で分類すると、日本文学に関するものが18篇と最も多く、次いで琉球研究、言語学が各9篇、日本文法とアイヌ研究が各6篇、考古学関係が4篇知られている。 1911(明治44)年に日本を去り、1935(昭和10)年にジュネーブで85歳で生涯を閉じている。 冒頭のチェンバレン氏の言葉は黎明期の日本言語学を切り拓いたチェンバレン氏が、日本文学と星の世界との関わりをどう見ていたかを知ることができる。 新村出(しんむらいずる)氏はチェンバレン氏の言葉を次のように引用している。 ************************************************ 昨年の夏一学友から国語で星の何はどんなものがあるかと尋ねられたことがありましたが、それより余程前にチャンブレン氏も日本文学に星辰の美を詠じてないのを怪まれたことが何かの書に見えました。又『国文学史十講』にも星の名称が上代にも近世にも一向見当たらないことを云って、我国の人民は農業国で昼の疲れに早寝をするので、天体のことには注意が少なかったのでありませうと解釈してあります。 (新村出「日本人の眼に映じたる星」『言語学雑誌』1900年8月掲載) ************************************************  『国文学史十講』とは、芳賀矢一氏の『国文学史十講』(1899年12月)のことで、1898(明治31)年8月の帝国教育会の夏期講習会における芳賀矢一氏の講義録である。左図の標題紙は「国立国会図書館デジタルコレクション」より。 1934年に始まった柳田國男氏指導による山村生活資料調査において「星の民俗」の視点を持ち得なかったのは、チェンバレン氏の日本人と星との関連は希薄であるという認識が、疑いを挟む余地のないものとされていたからだった。 しかしチェンバレン氏のこの認識に真っ向から反論した言語学者がいた。 新村出氏だった。 (20220130掲載) |
| 3、新村出「日本人の眼に映じたる星」 新村出氏(1876-1967)は1955年初版発行の『広辞苑』の編纂者として知られているが、星が好きなことでも有名で、終生京都の紫野に暮らしたことから晩年は紫野天文台長を自称した。東京天文台(現国立天文台)の台長を務めた関口鯉吉(せきぐちりきち)氏(1886-1951)は実弟であった。  ○ 『南蛮更紗』 新村氏は1924(大正13)年に『南蛮更紗』を改造社より出版した。同書の初版本は更紗染の素敵な表紙だが、残念ながら篠田は所有していない。左図は平凡社の東洋文庫版で1995年に復刻刊行。篠田所蔵本。 同書には36篇の作品が収められているが、「雪のサンタマリヤ」「切支丹文学断片」など南蛮に関わる作品に加えて、「日本人の眼に映じたる星」「星に関する二三の伝説」「二十八宿の和名」「星月夜」「昴星讃仰」「星夜讃美の女性歌人」の6篇の星に関する論考が含まれている。6篇のうち最初に発表された論考は「日本人の眼に映じたる星」で、初出は1900(明治33)年8月の『言語学雑誌』である。 拙稿「-覚書-1」で示したように、新村氏はチェンバレン氏の言を引用した上で、次のように述べている。 ************************************************ 天体の観測とか星学の知識とかいふ側では古代の日本人はとても支那(原文のママ)、バビロン、アラビヤ、希臘(ギリシア)又は印度などと肩を比するわけにはゆきませぬ。<<支那(ママ)の星学説、占星術および星辰崇拝が輸入されないうちの、日本人が天体に対する注意は、少くとも文献の徴すべき限りに於ては、皆無と申してもよろしい程であります>>。 ************************************************ 続いて新村氏は ************************************************ 我国に星学の形ばかり存してゐたのは全く支那(ママ)からの伝来で、それが徳川時代享保年中になって西洋の星学に接触したのであります。 ************************************************ と述べ、人事と天象とが相関するという中国の天文思想の日本への導入について検討し、占星術と暦についても触れている。その上で ************************************************ 自分は日本語が有する星の名目、日本人が星に対して抱いた思想感情の一解を究めることを最後まで残しておきましたが、今本論たるその事について縷述致さねばなりませぬ。 ************************************************ として、『日本書紀』巻第二の天津甕星(アマツミカホシ)に始まり、『万葉集』から明星(あかぼし)、夕星(ゆふづつ)をあげ『記紀』、古歌などから七夕、北斗、北辰、老人星、すばる、よばい星を例示した。 このうち北辰は北極星の異称、老人星は南極老人星と呼ばれた、りゅうこつ座のα星カノープス(Canopus)のことで、人の寿命を司るとされていた。よばい星は流星つまり流れ星りことで、清少納言『枕草子』第二三九段に「星はすばる」に続いて「よばひ星、すこしおかし。尾だになからましかば、まいて」とあることも示した。 二十八宿のうち『和名類聚抄』『枕草子』にも見える星宿について述べた後半部分は本論考の白眉ともいうべきものである。新村氏は ************************************************ 昴は和名<<スマル>>、又は<<スバル>>と申して、統の意であります。俗には六連星(むつらぼし)と唱えてゐますが、眼のよい者には七個見えるので。七星としてあります。それは西洋にいふプライヤーデスで、彼方でも俗に七つ星(セブンスターズ)と呼ぶさうであります。 ************************************************ として、『続日本紀』巻十二にある『丹後国風土記』を引用して浦島伝説が語られることを ************************************************ (昴が)特に<<海洋>>に関係するものなるや否やは不確であります。 ************************************************ と新村氏はこの段階では慎重な姿勢を見せている。 (20220202掲載) |
| ○ 「昴まん時粉八合」 「日本人の眼に映じたる星」では海洋との関連について慎重な姿勢をとった新村氏だったが、農家との関わりについては同論考で次のように述べている。 ************************************************ 昴星は農家にも多少知られてゐたとみえて信州の俗諺に「昴(スバル)まん時粉八合」といひ又それを「<<すまる>>まん時子八合」と訛った諺もある位です。即ち昴星が中する時蕎麦を植ゑると一升で粉が八合とれるといふ意味であります。 ************************************************ この文は新村氏の同論考の中で最も輝きを放っている。 新村氏の確信に満ちた、力強い宣言は、後述するように多くの影響を与えることとなった。 先を急ぐ前に、この文について少しばかりコメントを付しておきたい。 昴が中するとは南中する(または正中する)という意味である。 地球は1日で1回転の自転を行う。地球の自転によって太陽は24時間で元の位置に戻るが、恒星は23時間56分4秒で元に位置に戻る。24時間でないのは、地球は自転すると同時に太陽の周りを公転しているからである。このとき、地球から見たときの自転の軸は天の北極と天の南極を結ぶ軸であり、これを極軸という。 この運動によって恒星は同じ時刻であっても毎夜その位置を変えていく。 では「昴が南中する」とはいつ頃のことだろうか。 現在の学校教育では小学校4年生理科で夏休み前に「夏の星」を、冬休み明けに「冬の星」を学習することが多い。教科書にもそれぞれの単元に合わせて星空の写真が掲載されているが、それはおおむね20時頃のもので、夕食後に星空を観察することを前提としている。 しかしかつての農村が農事暦でいう時は、朝起きて仕事に出かける前、つまり夜明け前のことをいう。 この俚諺は、立春から数えて220日目の、雑節のひとつ二百二十日頃のことをさしている。ちなみに2022年の二百二十日は9月11日、1900年の二百二十日も9月11日(旧暦8月18日)だった。 また信州蕎麦は現在では1944年につくられた新しい品種である信濃一号が90%以上を占め、夏播専用として播種されている。今では在来種はほとんど栽培されなくなっているという。 (20220203掲載) |
| 【コラム】 「昴まん時」を検証する 「昴まん時」は二百二十日の日の出前に昴が南中する、ということを意味していた。 新村出氏がこの俚諺を「日本人の眼に映じたる星」として『言語学雑誌』に発表した年、1900年の二百二十日の「昴まん時」はどのようなものだったのか。 1900年の立春から数えて220日目は9月11日だった。 この日の太陽の中心高度が-18°の天文薄明が03時59分で、日の出が05時23分。天文薄明が始まって30分もすると夜空の星が少しずつ夜明け前の明るさに溶け込んでいくようになる。 アストロアーツ社の Stella Navigator 11 を用いて1900年9月11日の昴が南中する時刻を計算し、下図に示した。  長野県松本市(東経137度57分50秒、北緯36度14分10.1秒、標高585m)における1900年9月11日のプレアデス星団M45(昴)の南中時刻は04時11分。天文薄明開始から12分経過し、少しずつ星が消えていこうとする時間帯である。この時のプレアデス星団M45の高度は77.58°で、ほぼ天頂に近い位置に達している。 『壱岐島の方言集』などを残した山口麻太郎氏(1891-1987)は壱岐島に ************************************************ スバル天井夜八合、そば一升に粉八合、団子につくって四十八、六人家内に八つずつ ************************************************ という俚諺があることを紹介している(野尻抱影『日本の星-星の方言集-』1957年)。 ちなみに長崎県壱岐市(東経129度41分38.2秒、北緯33度44分56.4秒、標高44m)における1900年の二百二十日、9月11日の天文薄明開始は04時36分、日の出は06時00分。昴の南中は04時45分でその時の高度は80.07°にも達していて、まさしく「スバル天井」だった。 昴は二百二十日の夜明け前に南中し、ところによっては天井に達するまで昇り、農村に農事暦を告げる大切な存在だった。 (20220205掲載) |
.jpg)
昴(プレアデス星団 M45)
○ 「昴星讃仰」 『南蛮更紗』所収の新村出氏の論考に「昴星讃仰」がある。「ぼうせいさんぎょう」と読む。初出不明ながら1923(大正12)年4月『新村出集』からの再録である。 ここではスバルについて「東西共に農耕に結びつけられ、而も女性に擬せられて」いるとし、「希臘(ギリシア)では太古農民詩人ヘシオドスが英雄詩人ホメロスとの歌合せにスバルを歌って、みごとに勝を得た話がある」と世界最初の農事暦である『仕事と日』を書いたヘシオドスを引いて紹介している。 新村氏はギリシア神話のアトラス神の七人娘スバルの言い伝えに見る爾の耕作との関係を紹介した上で、「こんなにスバルは農民に親しまれた星である」と讃えた。 氏が「日本人の眼に映じたる星」で紹介した「昴まん時粉八合」について、ここではさらに次のように詳述する。 ************************************************ 日本でも近代信州の俗諺に、「スバルまん時粉八合」と云って、スバルの中する頃蕎麦を植えると一升で粉が八合取れると農家でいひはやしたやうだ。かく云う俗諺が今も信州その他の地方にあったら知りたいと思ってゐる。この俗諺は今から百二三十年前寛政時代の言葉であるが、同じ頃の大和にも農民が星を観察して種時などの時を定めたていふ話がある。 ************************************************ と述べた上で、京都の畑維竜(はた・これとき)の『四方の硯』(1804(享和4)年)という随筆から次のように引いている。 ************************************************ 星像を見ることは農民よりくはしきはなし。大和の国は水のとぼしき処なれば四月比より夏中農民夜もすがらいねずして星の像ばかり見て種おろし、あるひは夜陰の露おきたるに苗のしめりをしり、米穀の実のるとみのらざるとを、あらかじめ知る事なり。 ************************************************ として、その星を ************************************************ カラスボシ、ヒシボシ、<<スバルボシ>>、クドボシなどやうの名をつけて其の星は何時に何の位にあらはれ何時に何の方にかくるなどいひて、その目づもりにてはかると露たがはず。 ************************************************ と畑維竜の書を引用し、星の和名が農民の農事暦と結びついて息づいていたことを強く主張した。 新村氏は「日本人の眼に映じたる星」から20余年を経て「昴星讃仰」で「こんなにスバルは農民に親しまれた星である」と確信をもって昴を讃え、「スバルまん時粉八合」のような俗諺があったら知りたいと思ってゐる」と呼びかけたのだった。 (20220207掲載) |
| ○ 建礼門院右京大夫が讃美した星空 平家滅亡を目の当たりにした1人の女性がいた。建礼門院右京大夫(けんれいもんいん うきょうのだいぶ、1157?-?)である。新村出氏の『南蛮更紗』には平安時代末から鎌倉時代初めの、この女性歌人について述べた論考が2篇ある。「星月夜」(初出は『天界』1933年9月)、「星夜讃美の女性歌人」(初出不明、1933年8月)である。 建礼門院右京大夫は書道の伝統で名高い世尊寺家の娘で、父は藤原伊行(ふじわらのこれゆき)、母は夕霧。父伊行は『源氏物語奥入』『夜鶴庭訓抄』などを残し、母夕霧は箏の名手として知られた。 1173(承安2)年高倉天皇の中宮建礼門院平徳子(たいらのとくし/のりこ、1155-1213、安徳天皇の母、父は平清盛)に右京大夫として出仕。平資盛(たいらのすけもり)と恋愛関係になるが、1185(元暦2)年3月資盛が壇ノ浦で自害した後は供養の旅に出たという。1195(建久6)年頃後鳥羽天皇に再び出仕している。 新村氏は右京大夫が家集に残した即興の歌を1首紹介している。 ************************************************ 月をこそ ながめなれしか 星の夜の 深きあはれを 今宵知りぬる ************************************************ この歌について新村氏は「何の技巧もなく、唯率直に星夜の美を讃仰した作たるに過ぎない」としながらも「然しこれだけの讃美でも、これまでの歌人は、星夜に対してくれなかったのである」と吐露し、その題詞(だいし)には「日本の文学ではとにかく古今独歩ともいふべき文字がうかがわれ」(「星月夜」)、「日本文学絶無の文字が味はれる」(「星夜讃美の女性歌人」)と讃える。 ************************************************ 十二月の朔日(ついたち)の頃なりしやらん、夜に入りて雨とも雪ともなく打散りて村雲さわがしく一つに曇りはてぬものから、むらむら星うちきえしたり。ひきかづき臥したるきぬを、更けぬる程、丑二つばかりなどにやと思う程に、ひきのけて空を見上げたれば、殊に霽(は)れて、浅葱(あさぎ)色なるに光ことごとしき星の大きなるがむらもなく出でたる、なのめならず面白く、縹(はなだ)の紙に箔をうち散らしたる様に似たり。今宵はじめて見そめたる心地す。さきざきも星月夜見なれたることなれど、折りからにや異なる心地するにつけても唯物のみおぼゆ。 ************************************************ 題詞にある12月1日は文治元(1185)年12月1日(註1)、太陽暦の12月24日。丑二つ(註2)はおおよそ2時頃。すなわち西暦1185年12月25日02時頃の星空を見上げた情景である。旧暦の朔日(ついたち)は必ず新月。だからこの夜に月はなかった。 西暦1185年は元暦2年8月14日に元治に改元。ただし平家方では元暦の年号は使用せず、引き続き寿永を用いていた。 元暦2年(寿永4年)2月19日に屋島の戦い、3月24日に壇ノ浦の戦いで平家が滅亡。 建礼門院右京大夫は平資盛が壇ノ浦に自害、平家が滅びたこの年の暮れの星空を、後に追憶し歌と題詞を残した。彼女がこれを残したのは承久・嘉禄の頃であるから、60歳を過ぎていた。 新村氏は彼女の歌と題詞を次のように讃える。 ************************************************ これほどまでに星月夜を讃美した散文韻文は、この外私の未だ日本文学にみかけない所である。縹紙に金銀砂子をちらしたやうな冬の真夜中のはれわたった空を、追懐と愛着とに満ちた彼女は見上げて、「ただ物のみ覚ゆ」と嘆じた。縹紙に箔を散らした様だと形容したのも、書道の家に生まれた彼女として、始めて意味のある文句であった(「星月夜」)。 ************************************************ 彼女は高倉天皇の中宮建礼門院に仕え、宮中を退出した後に平家没落に遭った。 壇ノ浦を生き延びた徳子(建礼門院)は5月に出家し、9月に比叡山西麓の大原寂光院に入った。彼女(右京大夫)は心の苦しさに堪えかねてこの年の秋に寂光院に門院を訪ねている。その後の彼女について新村氏は次のように述べる。 ************************************************ その冬琵琶湖畔にさすらへて、比叡の麓坂本あたりにて、或晩真夜中に起き出でて星月夜を見上げて上記の歌を詠んだのである(「星月夜」)。 ************************************************ 西の空は比叡山が星空を隠していたろうが、湖面が広がる北、東、南には縹紙に「箔をうち散らしたる様」な冬の新月の星空が広がっていた。30~40年を経てなお彼女の心には、このときの星空は焼き付いていた。 新村氏は述べる。 ************************************************ とにかく物すごいほどに澄みわたった冬空に、ああいふ愛別、ああいふ世変を経験した彼女が、大星を、いわゆる「光ことごとしき星の大きなるがむらもなく出でたる」を、見上げた感情くらい高調に達したものはあるまい(「星月夜」)。 ************************************************ 新村氏は「星夜讃美の女流歌人」を次の言葉で結んでいる。 ************************************************ 縹紙に金箔を砂子のやうに散らした模様を連想したのは彼女の場合ほんとに活きた比喩である。 ……(中略)…… 追福に書きもしたらう縹紙金泥の経巻をも私たちの眼に映じさせる。私たちは信ずる、あの文句がこの一節に対して画竜点睛となってゐると。 繰返へしていふ。旧日本の文学に於て建礼門院右京大夫は、星夜の讃美の一節に於て無比の光彩を放ち、私たちは永久この女性歌人のスターを忘れてはならぬと云ふことを(「星夜讃美の女性歌人」)。 ************************************************ 新村氏の想いが、100年の時を経て、いま読む者の胸を打つ。 (註1) 文治元年12月1日を新村氏は「太陽暦にすると、西暦1185年12月31日に当る」(「星月夜」「星夜讃美の女性歌人」)としているが、これは誤りと思われる。西暦(太陽暦)1185年12月31日の月は上弦の1日前である( StellaaNavigator11 によるシミュレーション)。日本では西暦862年から1685年まで宣明暦が使われていた。宣明暦は太陰太陽暦であるから、朔日は新月であることが原則だった。文治元年12月1日は西暦1185年12月24日となる。 補足する。1185年12月24日(火)はグレゴリオ暦で、グレゴリオ暦は現行の西暦(太陽暦)である。先発グレゴリオ暦1185年12月24日(火)はユリウス暦では1185年12月17日(火)。ユリウス暦は1582年10月4日以前に使用されていたが、1582年10月15日(金)以降からグレゴリオ暦が採用された。 (註2) 丑二つ(うしふたつ)は丑の刻をさらに4つに分けた第2刻。定時法では午前1時半から2時頃、不定時法ではおおよそ1時から1時半の間。江戸時代後期にはおおよそ2時から2時半の間をさした。 (20220215掲載) |
| ○ 建礼門院右京大夫が仰ぎ見た星空 右京大夫は文治元年12月1日の深夜丑二つ頃、すなわち西暦(太陽暦)1185年12月25日深夜02時頃に琵琶湖畔の坂本付近で星空を仰ぎ見た。そこで彼女が仰ぎ見た星空とはどのようなものだったのだろうか。 彼女はこの夜のことを「夜に入りて雨とも雪ともなく打散りて村雲さわがしく一つに曇りはてぬものから、むらむら星うちきえしたり。」と題詞に表現し、夜に入って雨に雪が交じる不安定な天候だったことをうかがわせる。そして、「ひきかづき臥したるきぬを、更けぬる程、丑二つばかりなどにやと思う程に、ひきのけて空を見上げたれば、殊に霽(は)れて、、、」深夜に星空と出会い、その美しさを讃美している。 この時の天候を知る手がかりに、九条兼実(藤原兼実、久安5(1149)年-承元元(1207)年)の日記『玉葉』がある。 九条兼実は藤原北家・関白藤原忠通の六男として生まれ、従一位摂政・関白・太政大臣を歴任し、朝廷の中枢を担った人物である。『玉葉』は彼の長寛2(1164)年から正治2(1200)年までのおよそ40年間にわたって書き綴った公私にわたる日記である。 『玉葉』は国書刊行会から九条家旧蔵本を底本として3巻が発行されている(1906~1907年)。下図はそのうち第三巻の文治元年12月の冒頭部分である(「国立国会図書館デジタルコレクション」より引用)。 |

| 『玉葉』は日付、干支、天候、日記の順に書かれていて、ここで注目したいのは日付と天候である。 上図から12月1日、2日と「陰晴不定」と続き、3日になってようやく「天晴」とある。 文治元年11月と12月の『玉葉』から抜き出した天候は下図の通りである(暦はすべて旧暦の宣明暦)。 11月28日から12月2日まで5日間連続して「陰晴不定」が続いている。ちなみに11月は「天晴」が22日あり比較的天候が落ち着いていたことがうかがわれるが、12月の「天晴」は9日にどとまっている。ちなみにこの年の初雪は11月17日(太陽暦では12月10日)で「初雪積庭上」とある。 |

| 12月20日には7月9日に起きた大地震、文治地震の余震と思われる大地震について書かれている。7月の大地震は元暦2年7 月9日(ユリウス暦1185年8月9日)に発生し、この地震があったため翌月「文治」に改元されている。文治地震については
鴨長明(1155?-1216)が『方丈記』に詳しく記している。 『玉葉』12月20日の大地震の日記には「此震非他武士諸国横領之徴」とあり、流言飛語が飛び交っていたことがわかる。 文治元年は平家滅亡、文治地震と大きな出来事が続く中、不順な天候のまま暮れを迎えていた。 |
| 下図は右京大夫が讃美した文治元年12月2日02時の星空を再現した星図である。天文シミュレーションソフト StellaNavigator11 を用いて、場所を琵琶湖畔坂本寂光院(天台宗、比叡山延暦寺の里坊の1つ)に設定した。地点は北緯35度4分14秒、東経135度52分11秒、標高135mである。 |



| 全天、西天、東天の各星図を見ると、おうし座、オリオン座、おおいぬ座などの冬の星座が西天に沈もうとしていること がわかる。昴(プレアデス星団)は仰角15度と大変低く、比叡の山並みに沈んで姿を隠していたことだろう。冬の星座のう
ち最後まで残るふたご座のカストルとポルックスは65度付近に見られるが、これらもやがて比叡山へと傾こうとしている。 天頂近くには春の星座のしし座とかに座がある。北斗七星から春の大曲線をたどると、うしかい座の1等星アルクトールスと、おとめ座のスピカが見える。ベテルギウス、リゲル、プロキオンがつくる冬の大三角のうちリゲルは比叡の山に隠れていたことだろう。 代わって春の大三角のアルクトールス、デネボラ、スピカが日が東の空から天頂に近づいている。冬の賑やかな星座から季節は春へと変わり始めている。 この星空を眺めた右京大夫は「光ことごとしき星の大きなるがむらもなく出でたる」とした。 そこにある、「星の大きなる」とは何だろうか。文治元年12月に客星(ふだん見慣れない星、超新星・新星・彗星など)が現れていたのだろうか。 ○ 歌人の藤原定家(応保2(1162)年-仁治2(1241)年)は摂政九条兼実の九条家へ家司として出仕し、九条兼実の連歌の席に出席するなど兼実の庇護を受けていた。その定家が残した日記が『明月記』である。『明月記』には治承4(1180)年から嘉禎元(1235)年までの56年間の記録が記されているが、そこにはさまざまな天文・天体現象の記録もある。これは天変は不吉な前触れであるとして関心が高かったからである。 かに星雲が生まれた超新星爆発(SN1054)は1054年7月4日(ユリウス暦)に世界中で観察されている。『明月記』にある記述が有名だが、藤原定家が生まれる前のことで陰陽師の記録が日記に残された。この外『明月記』には寛弘3年4月2日(ユリウス暦で1006年5月1日)、天喜2年(ユリウス暦1054年)、治承5年6月25日(ユリウス暦1181年8月7日)の超新星爆発の記録があるが、文治元年12月に客星が現れた記載はない。つまり、右京大夫が「光ことごとしき星の大きなるがむらもなく出でたる」のは客星とは考えにくい。 再現星図をよく見ると、1185年12月2日02時の東天には春の大三角に割って入るように、木星と土星がある。西には火星もあるが、高度は10度を切っていて坂本からは見られなかったはず。 StellaNavigator11 のシミュレーションによると、この時の木星の光度は -2.2等級、土星は 0.8等級。木星の出は22時24分、没は11時03分。土星の出は23時25分、没は11時40分。この時の春の大三角を構成するアルクトールスの光度は -0.05等級、デネボラは 2.14等級、スピカは -0.98等級であり、木星の明るさが際立っていた。しかも木星の高度は40度を超していて、そのすぐ下には高度30度付近に土星があった。ちなみのこの日の月齢は1.3だった。 右京大夫は雲が晴れた深夜2時、冬の賑やかな星座が西の比叡の山へ沈み始めた頃、東南の空にひときわ明るい木星とそれに続く土星を仰ぎ見た。冬の星たちが密集して輝くのに対して春の星たちが控えめに光る中、この2つの惑星は「光ことごとしき星の大きなるがむらもなく出でたる」というように、見る彼女の胸に迫ったことだろう。 彼女は12月2日未明に星空を見た、それ以前にも空を仰いだかもしれない。しかし『玉葉』に記載されているように11月28日から「陰晴不定」の日が続いていた。きっと夜空に星を眺めることは叶わなかっただろう。また12月に入っても10日までの10日間に「天晴」は4日しかなく、不安定な天候が続いた。右京大夫にとってあの夜こそが唯一の星空だったのかもしれない。 西の比叡の山に沈みゆく冬の星たち。その向こうには西海に滅亡した平氏と、壇ノ浦に自害した平資盛があった。 彼女は琵琶湖畔から仰ぎ見た星に何を見たのだろうか。 (20220217掲載) ( 続く ) |

揖斐谷の天の川と木星・土星
| 揖斐谷から見た天の川と夏の大三角。右の山際には、街明かりの光害に負けずに明るく輝く木星(下)と土星(上)。右京大夫の生きた時代は光害とは無縁だっただろう。どんな星空が見られたのだろうか。 2021年5月6日03時08分撮影 |